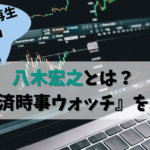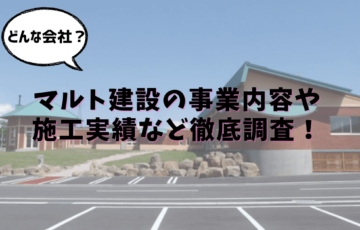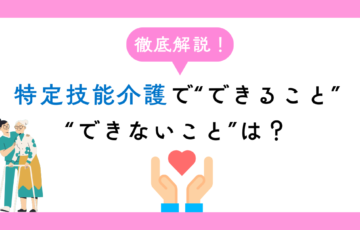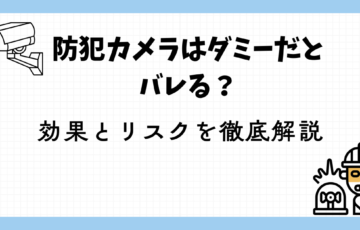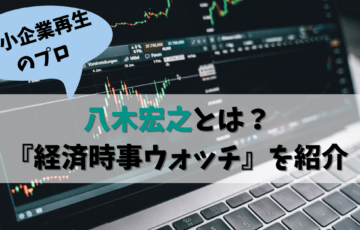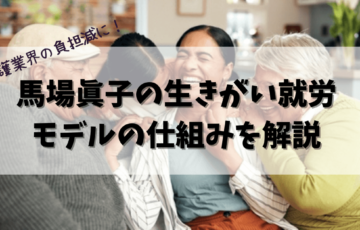現在日本は高齢化が進み、介護の現場は人手不足という深刻な課題を抱えています。
そんな状況の中で注目されているのが、馬場眞子さんが取り組んでいる「生きがい就労」という新しい仕組み。
この仕組みは、元気な高齢者が無理なく働きながら、介護スタッフの負担を減らし、地域と施設のつながりを深めるという画期的なアイデアなんです👀
この記事では、馬場眞子さんがどんなふうにこの仕組みを作り、どんな成果が出ているのかを、わかりやすくご紹介していきます(*^^*)
そもそも馬場眞子ってどんな人?

馬場眞子さんは、千葉県柏市にある社会福祉法人「小羊会」の常務理事をつとめていて、長年にわたり地域に根ざした福祉の実践を続けてきた人物です🌹
なかでも注目されているのが、地域のシニアが無理なく働ける「生きがい就労」という仕組み。
その実績は、全国の福祉関係者からも注目を集めています。
ここでは、生きがい就労の仕組みそのものを紹介する前に、馬場さんがどんな思いで活動してきたのか、少しだけ背景をのぞいてみましょう。
現場と地域をつなぎ続けてきた福祉のキャリア
馬場眞子さんは、特別養護老人ホーム「柏こひつじ園」を拠点に、地域と施設のあいだをつなぐ福祉のあり方を実践してきました。
介護を必要とする方だけでなく、「まだまだ社会と関わりたい」という元気な高齢者にも注目し、誰もが関われる“開かれた介護”を目指してきたんだそうです(*^^*)
講演で広がった「生きがい就労」への関心
馬場さんの活動が広く注目されるようになったのは、UR都市機構「街みちネット」が主催する第23回見学・交流会での講演が大きなきっかけでした。
現場の声やリアルなエピソードや成果を交えながら、「生きがい就労」がいかに現場の負担を減らし、地域とのつながりをつくっているかを丁寧に発信📶
シニア世代の活躍に新たな可能性を示すその姿勢に、多くの自治体や福祉関係者が関心を寄せているんだそうですよ( •̀ ω •́ )✧
馬場眞子が始めた生きがい就労モデルってどんな仕組み?

「生きがい就労」は、元気なシニアが介護施設で生活のサポートをしながら、介護スタッフの負担をやわらげたり、地域とのつながりを深めたりする新しい仕組みです。
このモデルをつくったのが、馬場眞子さん。
介護の現場では人手不足が深刻ですが、一方で「まだまだ働きたい!」という高齢者もたくさんいます。
その“ギャップ”をうまくつないだのが、生きがい就労というわけなんです◎
ここでは、そのしくみや背景、どんなふうに実践されているのかを見ていきましょう🔍
仕組みづくりのきっかけは介護の人手不足と地域の高齢化
生きがい就労を始めたきっかけは、介護現場の人手不足。
馬場眞子さんが理事をつとめていた施設のある千葉県柏市・豊四季台団地は、高齢化率が高く、一人暮らしのお年寄りも多く住んでいるエリアです。
「少しでも誰かの役に立ちたい」というシニアと、「手が足りない」と悩む介護現場👵👩🦱
この両方の声をうまくつないだのが、馬場さんのアイデアでした✨
どんな仕事があるの?シニアが活躍できる場いろいろ
生きがい就労では、資格がなくてもできる仕事がたくさん用意されています。
たとえば、こんなお仕事があります。
| おしごと | 内容の一例 |
|---|---|
| 調理の手伝い | ご飯とお味噌汁の用意、盛り付け、配膳など(ユニットごと |
| 園芸 | 花の世話や草取り、季節の飾りつけなど |
| 洗濯・おそうじ | 衣類をたたむ、共有スペースの掃除など |
| ティーサロン運営 | 地域の人にランチを提供したり、おしゃべりできる場づくりなど |
お仕事というと不安に思う方も少なくないですが、どれも今まで家庭でやってきた家事の経験をそのまま活かせる仕事ばかり✨
ずっと専業主婦で「仕事は初めて」という方でも安心してチャレンジできます(*^^*)
無理なく続けられて、誰かの役に立てるのって、素敵ですよね🌸
続けやすさのヒミツは“ムリしない”仕組みづくり
馬場眞子さんは、「高齢者が楽しみながら、無理なく働ける環境」をとても大切にしています。
そのため、働き方にはこんな工夫があります。
働き方の工夫
- 1回の勤務は2~3時間くらいでOK
- 「今日は確実に行ける日」「行けるかも?」「都合が悪い日」をあらかじめ自己申告
- 複数人でチームをつくって、交代しながら担当
- 6か月ごとの契約更新&有給休暇もアリ
- 時給は千葉県の最低賃金以上をしっかり保証
体力的にも精神的にもムリのない働き方だからこそ、「また明日も行こうかな」と思えるというわけですね(*^^*)
こうした仕組みが、シニアの“生きがい”を支えているのです。
馬場眞子の生きがい就労がもたらしたうれしい変化って?

馬場眞子さんが生きがい就労モデルを取り入れたことで、介護の現場ではさまざまな前向きな変化が生まれています。
介護スタッフはもちろん、働くシニアの方々や地域の人たちにとっても、「これ、いいね」と感じられるようなうれしい変化がいろいろ起きている模様✨
ここでは、その中から代表的な3つをご紹介しますね(^^)
介護スタッフの負担がグッと軽くなった
仕組みを取り入れたことで、朝のごはんづくりやお掃除、洗濯など、介護スタッフだけでは手が回りにくい部分をシニアスタッフが担当してくれるようになりました。
介護施設って特に朝は人手が少なくなりがちなのですが、シニアが見守りもしてくれるおかげで、職員は本来のケアに集中できるようになったのだとか!
「安心して仕事ができるようになった」と感じているスタッフも多いそうです。
シニアが元気に!やりがいもアップ
シニアの方の中には、子育てやお仕事がひと段落して、自由な時間が増えた反面、毎日が同じことのくり返しで、人とあまり話す機会がなくなっている…そんな方も少なくありません👵👴
人と会話したり、ちょっと頭を使ったりする機会が減ってしまうと、どうしても認知症のリスクが高まってしまうこともあるんです。
生きがい就労に参加しているシニアたちは、無理なく社会とつながることで、健康維持や認知症の予防にもつながっているそうです。
「お小遣いがもらえるのがうれしい」「若いスタッフとおしゃべりするのが楽しみ」といった声もあり、なにより「誰かの役に立っている」という実感が毎日のはりになっているみたいですね(*^^*)
地域の人たちとつながりが広がった
施設内にある「ティーサロンこひつじ」は、地域の人たちと入居者が自然に集まれる、ほっとできる場所。
シニアスタッフが地域の方と顔を合わせることで、日々のちょっとした変化にも気づきやすくなります。
このような交流が、見守りのネットワークとしても機能しているからこそ、「地域の目で支える介護」にもつながっているんですよ😉
閉ざされた施設ではなく、地域に開かれた介護というのは、まさに馬場眞子さんの目指す形と言っても過言ではありません。
うまく続けるコツって?馬場眞子さんの取り組みから学べること

生きがい就労を取り入れてもうまくいかないケースもあるなかで、馬場眞子さんの取り組みは、しっかり根づいて長く続いています。
その理由は「高齢者に仕事を任せる」という単純な発想ではなく、準備から日々の運用まで細やかな工夫を大切にしてきたから。
ここでは、そんな馬場さんの実践から見えてきた、うまく続けるためのコツと、気をつけておきたいポイントをご紹介します。
ムリなく働ける環境づくりがカギ
シニアの方に長く気持ちよく働いてもらうには、「自分のペースでできる」ことが大事です。
馬場さんの施設では、勤務日を自己申告制にしていて、「絶対に出られる日」「出られるかも」「お休みしたい日」を自分で選べる仕組みになっているのだとか!
体調がすぐれないときには、無理せず休んでOK。チームや施設側がフォローする体制が整っているので、安心して続けられるんですね(*^^*)
得意を活かしてできることからスタート
生きがい就労をスムーズに始めるには、「この人には何ができそうか」をしっかり見極めることが大切です。
馬場さんは、一人ひとりの得意なことや生活スタイルに合わせて、無理のない役割を割り振っています。
仕事の目的もきちんと伝えて、やることがぼんやりしないように工夫。
たとえば、タイムカードの使い方などもていねいに教えていて、「わからないまま放っておかない」のがポイント。
「できないこと」ではなく「できること」に目を向ける、その姿勢が、あたたかくて前向きな雰囲気をつくっています😉
まとめ|馬場眞子の取り組みがもたらす未来

ここまでご紹介してきた馬場眞子さんの「生きがい就労」モデルは、介護の人手不足と、高齢者の「まだ働きたい」という思い。
その両方をやさしくつなぐ、実用的であたたかな取り組みだというのがご理解いただけたのではないでしょうか✨
シニアが無理なく働ける環境を整えることで、介護スタッフの負担が軽くなり、地域との交流も自然と広がっていきます。
この取り組みは介護の現場にとどまらず、「人が人を支える社会」を形づくるヒントにもなり得るもの。
年齢を重ねても、誰かの役に立てる場所がある──その当たり前をかたちにしてきたのが、馬場眞子さんの挑戦と言えるでしょう。